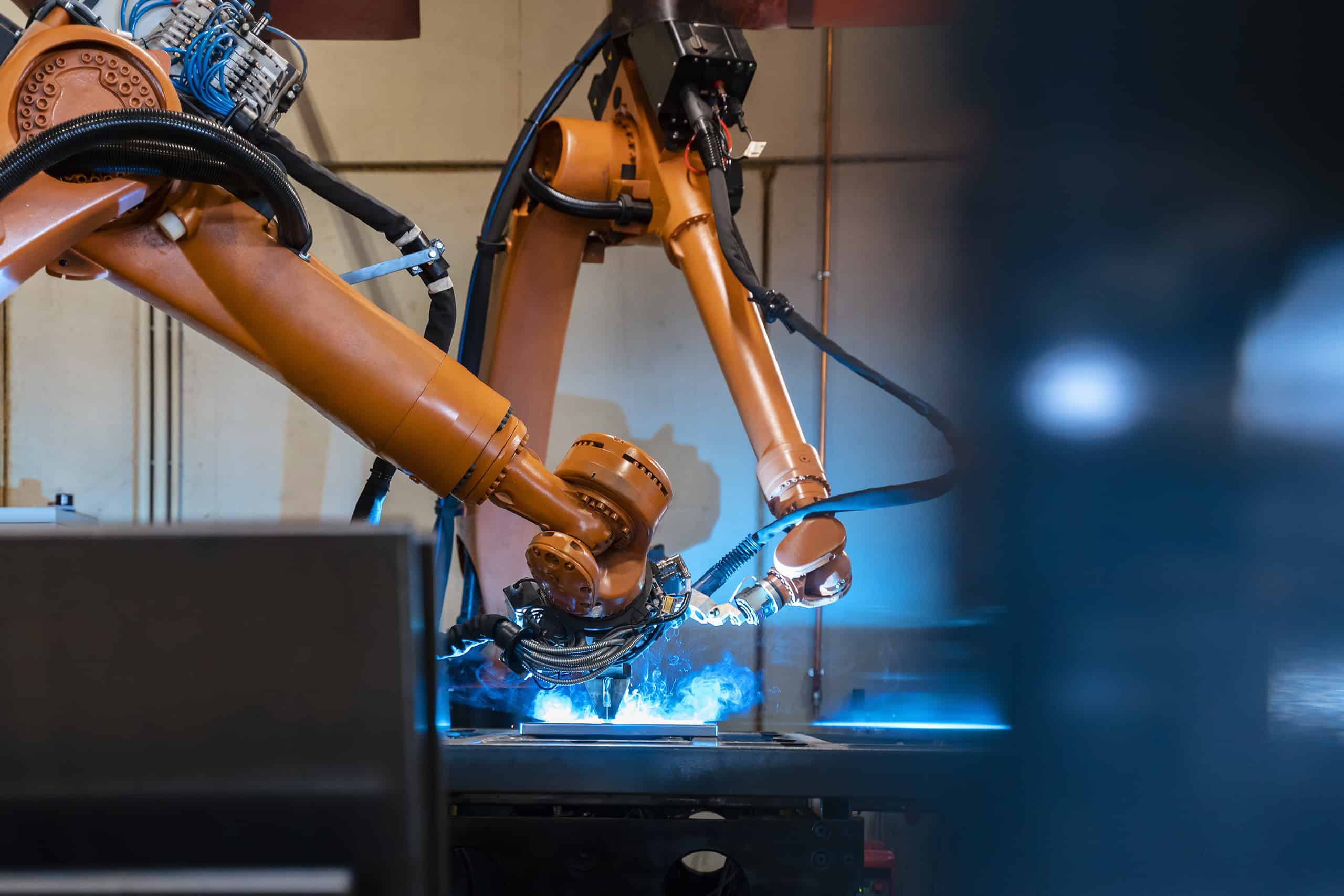こんなあまりにもよく知られた状況を想像してみてください:
ある企業が、業績不振を理由に従業員の解雇という難しい決断を下した。これは、これまで何度も指導や懲戒処分を受けてきた当該従業員にとって、驚くべきことではないはずだ。にもかかわらず、その従業員は驚きと怒りを露わにした。解雇面談において、彼は(十分に記録されている)業績問題が解雇理由ではなく、「苦情」を申し立てたことへの報復だと主張した。パニック状態が起きた。
同社の人事部長はこの従業員からの苦情を一切聞いたことがなく、人事ファイルや人事記録にも苦情を示すものは何もない。困惑した人事部長は調査を続け、数週間前、上司との何気ない会話の中で、この従業員が「他の従業員より長時間働いているのに、その追加労働時間が報酬に反映されていないようだ」と述べたことを突き止めた。
これは古くからの疑問を提起する――一般的な「愚痴の吐露」が、会社が調査すべき保護された苦情となるのはいつなのか?その答えは、一部の雇用主を驚かせるかもしれない。労働省によれば、従業員は自身の賃金、労働時間、その他の権利について問い合わせたことを理由に報復を受けることはできない。(さらに、全米労働関係法は、雇用条件に関する懸念の表明を含む協調的活動に従事する対象労働者を保護している。)したがって、一般的な観点では、この種の苦情は常に対応され、場合によっては調査されるべきである。
ただし、単なる意見や不満の吐露が、保護される苦情のレベルに達したかどうかを判断するのは難しい場合が多い。経験則として、従業員が賃金や職場環境(本事例の従業員のように)について言及した場合には、雇用主は慎重を期し、問題の調査を行うべきである。
少なくとも、上司はこのような性質の申し立てを人事部または社内外の法律顧問に報告し、調査が必要かどうかを判断するよう指導されるべきである。場合によっては過剰な対応に感じられることもあるが、これは「予防は治療に勝る」という方針であり、最終的には会社を保護することになる。